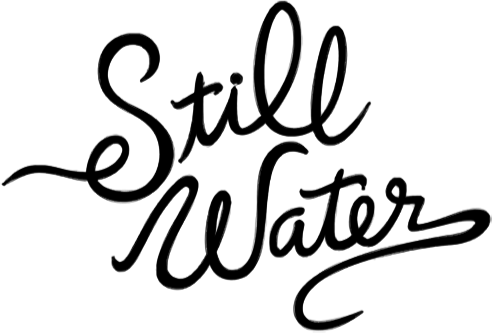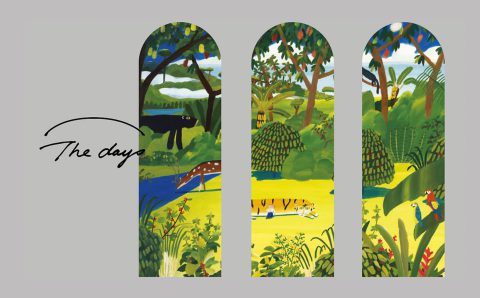子役を育てることになったわけ
「子どもは育てたように育つ」と、stillwaterを起業して最初のお仕事をご一緒した、大分県佐伯市に336年続く糀屋本店の女将、浅利妙峰さんに教えていただいたのは、まだ娘を授かる前の話。のちにこれほどまでに実感することになるとは思いもしませんでした。
現在10歳になった彼女は、子役と呼ばれるお仕事をしています。でも、彼女を子役にしようと思っていたわけではありませんでした。ただ、父は舞台演出に携わる仕事に就き、母は歌が好きで、踊りを習い、表現者を心から尊敬している、という家庭に生まれたというだけ。彼女は、小さい頃から歌と踊りが好きでしたが、子どもはみんな多かれ少なかれ、歌って踊るものだと思っていたし、特段、そのことに秀でていると思っていませんでしたが、1歳から保育園で習った歌や踊り、先生の真似を家でよくしていました。あとは、3歳くらいから彼女の歌に私が乗っかってハモりの英才教育を施していたくらい(笑)。舞台はお腹の中にいた頃からよく観に行っていたので、劇場で観劇をすることには慣れていたかもしれません。
5歳になった頃、習いごとをするならと思って始めたのが、クラシックバレエとミュージカル(歌とダンスと演技)でした。将来、どんな道を選ぶにしてもコミュニケーション力は必須だし、体幹が鍛えられれば人間としての軸も整うはず、という直感的な理由からでした。ピアノや水泳もやって、一通り楽しそうにやっていましたが、バレエとミュージカルだけは他の習い事とは違い、先生方のご指導のおかげでみるみるのめり込んでいき、家で歌って踊っている様子も少しずつ様になってきました。プロダクションにも所属し、コンクールクラスや劇団にも所属して、いつしか彼女の夢は「ミュージカルスターになって、お客さまを笑顔にすること」になりました。

持って生まれたギフトをしっかり肯定する
これまでにオーディションもたくさん受けて、悔しい思いもたくさんしました。そこに集うお子さんや親御さんたちはみんな百戦錬磨の方ばかり。彼女もそのうちのいくつかは実技まで呼んでいただけるようになり、あと一歩のところで役に届かない経験が続くと、親のほうが悔しい気持ちになって、いつまでも気持ちが切り替えられません。すると彼女から「ママ、選ぶのはカンパニーの皆さんなんだからしょうがないよ。次に行こう!」と言われる始末。たくましい限りです。
家では、とにかくずっと歌っているか踊っているので、私が仕事をしている時は集中するのが大変な時もあるけれど(笑)、実際に彼女の伸びやかな歌声が曲調にぴたりとハマると、思わず手を止めて聞き入ってしまう。きっと、歌はもっと磨いたらさらに光ると思っています。ダンスは、全面に好きが出てる。身体と気持ちがひとりでに動き出している。総体的に見て、彼女の持ち味はテーマや役柄に合わせて、その人物に成り切ることができる能力。没入し、役に魂を吹き込み、自分自身を染めていく。大袈裟かもしれないけれど、魔法、そんな言葉も連想させられる。観ている人も、本人もその魔法の中に誘われていく感覚。
彼女が初めて出演した舞台は7歳の時。アンサンブルと呼ばれる役でしたが、実際に大勢の観客がチケットを求めて観劇する、その舞台に立てるということ自体が本当に夢のようでした。彼女はカンパニーの中で最年少でしたが、私たちが見たことのない表情でいきいきと舞台に立ち、堂々たる佇まいで、それはそれは楽しそうに歌って踊っていました。彼女にとって舞台に立つことは、持って生まれたギフトなのだと実感しました。
その人そのものを生きることが最もパワフル
幼い頃、歌うことが好きだった私は、大きくなったら歌手になりたいと母に話すと「誰でもなれるわけじゃないのよ」と言われたことが、今も記憶に残っています。母は世間一般のごく当たり前のことを言っただけだったと思いますが、それを全身全霊で受け止めた幼い頃の自分を憶えています。夢を追わない決断をしたから人の才能に気づくようになったのか、人の素晴らしい部分に気づく能力を持って生まれたのかはわかりませんが、私は、その人の中にある光っている部分を感じ取ることが得意だと思います。もしかしたら本人もまだ気がついていない良さ。そこがもっと拓かれてほしいと思うし、その先の可能性も見えるので、インタビューなどでそこが見えた時に、興奮気味に熱量を持ってお伝えすることがあります。娘の場合はとても身近な存在だったので、こうして伴走するに至りました。いま彼女が歩む道がこの先どこへ繋がっているのかわかりませんが、「表現」という手段が、この先、どんな職業に就こうとも必要になるコミュニケーションの根幹にあるのではないかと、予感しています。今は、お稽古場に通うことがとにかく楽しくて仕方がないという様子に、こちらが元気をもらっていますが、人は、その人そのものを生きることが最もパワフルなのだと、彼女が証明してくれているのだと思います。

夢を手繰り寄せること
ご縁のある作品もあれば、悔しい思いをした作品もあり、トータル30本くらいはオーディションを受けてきたと思います。子役に求められる条件はとても厳格で、1cm単位の身長制限に加えて、求められる役を理解して表現できるか、段取りをしっかりとこなせる年齢かどうかなどを見られ、書類と、歌やお芝居、ダンス、自己PRなどを撮影した動画を送ります。小学校1年生で400字詰めの原稿用紙に志望動機を自分の字で書くものもあり、考えをアウトプットする訓練になっています。役の雰囲気に合うかどうかを見られ、実際に会ってみたいと思ってもらえて初めて、実技審査に進むことができるのです。しかも、あるオーディションを受験中に他の案件が重なったら受けることができなかったり、出たい作品の再演と年齢や身長がずれてしまったりと、作品に役がいただけることはほぼ奇跡に近いのです。
そんなすべての奇跡が重なった先に、建て替えに入る直前の帝国劇場のクロージングラインナップ作品に、素晴らしい役をいただくことができました。「表現すること」を生業とするプロフェッショナルなカンパニーの皆様と一緒に集中してお稽古を重ねて、本番に向けて作品性を高めていく様子はワクワクしましたし、地方公演を含めるとお稽古から約半年の間、歴史ある作品に関わることができたことは、親の私たちにとっても素晴らしい経験となりました。プロフェッショナルな皆様に一人の役に仕上げていただき、主役の方に真剣勝負を挑む役どころ。2000人規模の劇場の舞台に立ち、そこから見た景色は、彼女にとっても私たちにとっても唯一無二の経験となりました。
「心が動く」は理屈じゃない
娘が一流の役者さんたちと肩を並べてスポットライトを浴びて舞台に現れた時、堂々として勇ましく、光を放っているように見えました。小さな身体で、精一杯、役の中に魂ごと入り込み、歴史と時空を超えて、ひたすらに演じている姿は、年齢やキャリアを感じさせない圧巻の迫力がありました。集中力、舞台上での連帯感、自分自身の限界や可能性を、全身で感じているようにも見えました。その一つひとつを意識できていたのか確認はしていませんが、「彼女自身の魂が求めていることを、実際にやり遂げている」という喜びが伝わってきました。それを見ていると、大人になっても、自身の可能性を追求すればするほど拓かれていくのだと思えてくるからとても不思議です。人の本気は、人の心も動かす。
現在も、日本で上演されてからもうすぐ半世紀に届くミュージカル作品に出演することになり、鋭意お稽古中です。彼女は学校に行きながら、両親も仕事をしながらのお稽古通いの日々はまさにカオスの極みです(笑)。よくがんばっているなと労ってあげたい気持ちと、さらに高い要求をしたくなる親としての気持ちがクルクルと巡る日々。それでも心が豊かでいられるのは、彼女が生き生きととても楽しそうだから。そして、家族全員「舞台芸術」が好きだからだと思います。
私は、彼女が歩む道を通して私自身の興味関心を確信に変えてもらっている気がしています。そして私が、幼い彼女の中にあった表現者としての一筋の光を見つけることができていたのなら嬉しいなと思います。

「総合芸術」の中に何があるのか
私が、舞台芸術を素晴らしいと思うのは、一人ひとりの個性の輝きを結集し、一つの芸術作品へと昇華させ、たくさんの人々の感性と感受性に語りかけることができる「総合芸術」だからです。
オンラインで世界中の人とコミュニケーションができる時代に、生身の人間が表現を通して目の前にいるお客さまに語りかけることができる機会。そこに立つ表現者は、これまでの経験と惜しみない熱量を注ぎ、魂を震わせる。それを共演者やスタッフの方々と共鳴させることで、総合芸術は成り立っている。そのエネルギーが大きければ大きいほど、観客を魅了する渦も一層大きなものになる。その作品に触れた人が受け取ったエネルギーを、次の行動に変える一つのきっかけになるかもしれない。二次的にも三次的にも人の魂の本質に語りかけるタッチポイントがある。その起点となることを仕事に持っている人を心から尊敬している。そんな「総合芸術」を生み出す現場に私も関わり続けたいと思っています。そして、今、私が経験させてもらっていることを、深い対話と企画やプロデュースを通して、私が心から尊敬する「表現することを仕事にもつ方々」の力になりたいと思っています。
stillwaterの新しいプログラムをリリースするにあたり、なぜ私が「表現者」に関心を寄せることに至ったのか、ここに書き留めておきます。「自分の本質」にフォーカスして生きる人と一緒に走りたい、と思っています。
インタビューおよびコンサルティングの詳細はこちら。
https://stillwaterworks.jp/about/dialogue/
仕事の種類
・プロデュース
・マネジメント
・メンターとコーチ
それぞれを、親としてもstillwaterの白石としても伴走
プロジェクトの時期
・2014年~