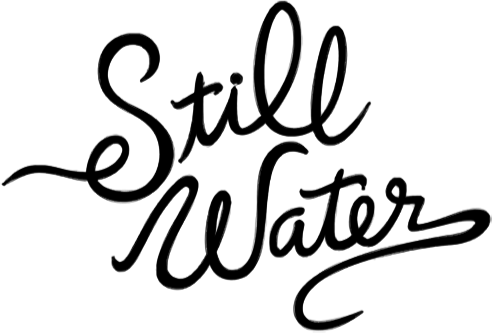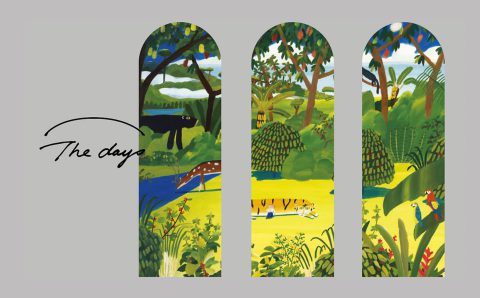ビジネス街で取り組む大人の食育活動
東京駅から皇居まで、大手町・丸の内・有楽町の3つのエリアにまたがるビル群を管理・所有する三菱地所が、「食を通じて、心身ともに健康になれる社会を目指す」ことを目標に、街をあげて「食」の重要性を掲げていることをみなさんはご存じでしたか?
そのスタートは2008年。日本経済の中心地であり、当時の就業人口は28万人(現在は35万人)。日本最大級のビジネス街が今後の“街のありかた”を問うた先にあったのが、大人のための食育活動「食育丸の内」プロジェクトだったのです。
翌年からファーマーズマーケットの開催、食育ランチ会、トークイベントなど幅広い食の企画を進行しながら、料理評論家の故・服部幸應さんを会長に迎えた「丸の内シェフズクラブ」も発足され、参画した25名の精鋭シェフたちが協力し合い、食に関する意識や技術の向上、生産者と消費者をつなぐ場の提供など、丸の内という街のなかで「食」を軸としたさまざまなプロジェクトが推進されてきました。
※第1期メンバーはこちら

はかり売りでフードロスに貢献する「丸の内 gramme Marché」

25mにも及ぶテーブルで食事を楽しむ景色が広がった「ロングテーブル“絆 KIZUNA”」
食べものがあなたの身体と思考をかたちづくる
スティルウォーターは「食育丸の内」に2014年から携わり、同時に「丸の内シェフズクラブ」の事務局を担当しています。
食への興味・関心が高く、人生の歓びのひとつとして食を捉えている私たち。どんな人がこの街で食を通した活動を行っているのか、どうすれば生産者や地域とつながるのか、シェフたちが食を通じて発信したいメッセージをどう届けていくのか。毎日の生活のなかで誰もが自分ごとである食の分野だからこそ、丁寧に繋ぎ合わせ、街の魅力として表現していく方法を探っていきました。
そこでまず企画・編集を担当したのが季刊誌のフリーペーパー『丸のなか』です。
「食べものがあなたの身体をと思考をかたちづくる」というコンセプトのもと、著名人のインタビューやシェフとの対談から、生産地との連携企画、健康な身体づくりに関する情報まで、街で働く人たちそれぞれが関われる接点を紹介し、誌面を飛び出したイベントも多岐に渡りました。一方で、産地訪問、親子で参加できる料理教室、街で提供されるランチレシピを考案したりと、街と人を食でつなぐ架け橋として、丸の内シェフズクラブメンバーの活動の場も広がっていったのです。
写真:丸いお皿のなかで表現される、丸の内シェフズクラブメンバーによる料理が毎号表紙を飾った
「食育丸の内」から「EAT&LEAD」へ
丸の内エリアを拠点に「食」「健康」に関連する活動、そして200回以上のイベントなどを重ねてきた「食育丸の内」プロジェクト。2021年には「食べることを大切にする街・丸の内を目指し、食の分野をリードする存在になっていく」という想いを込め、名称を「EAT&LEAD」へと変更しリブランディングを行いました。
ひとりひとりの食の感受性を高め、消費について考える力を養うこと、地域と繋がって都市との循環を生むこと、就業者や来街者と接点を持つこと。食を中心に置きながら、街を舞台に社会課題の解決に取り組んでいこうと、いま現在もさまざまなプロジェクトが進行しています。

そして2024年、顔ぶれを新たにした丸の内シェフズクラブ第2期がスタート。ここでは、国内外に活動の場を広げ社会問題にも精力的に取り組むシェフ・パティシエ・バーテンダーの方々をキャスティング。第1期のシェフたち同様、一皿の創造力に私たちが歓喜するほどの感性を持つ彼らとともに、この時代だからこその食を取り巻く問題へともに向き合い、連携をしていきます。


「食べる事から学ぶ、生きる力EAT&LEADトークサロン」では、料理人と異分野のゲストがさまざまなトークテーマで語り合い参加者とも交流を図った。


2024年に実施した「食のフィールドワーク in 雲仙」。シェフたちが現地の食文化を知り、食を取り巻く問題にも耳を傾ける。


フィールドワークの翌年には、東京で一夜限りの「POP UP レストラン」を開催。生産者たちも地域の魅力や現状を語り、シェフたちは現地で得たインスピレーションから料理を提供する。
食の感受性を高めて「食ベる」ことを大切にする街へ
そしてEAT&LEADを担う私たちは、今日何を食べようか?誰と食べようか?と、さらに貪欲に食に向き合います。ビジネスパーソンと来街者、それぞれがそれぞれらしく関わることができる企画を考えながら、この街と人々が出会うきっかけづくりを続けていきたいと思うのです。
仕事の種類
・ブランディング
・誌面の企画・編集、インタビュー
・コミュニケーションデザイン(コンセプト、ウェブサイトなど)
・コンテンツ企画、キャスティング
仕事の時期
・2014年〜
写真協力:三菱地所株式会社