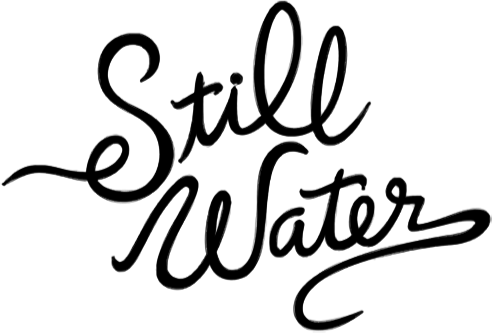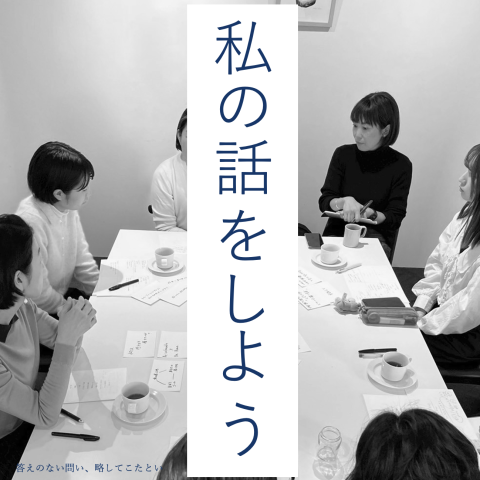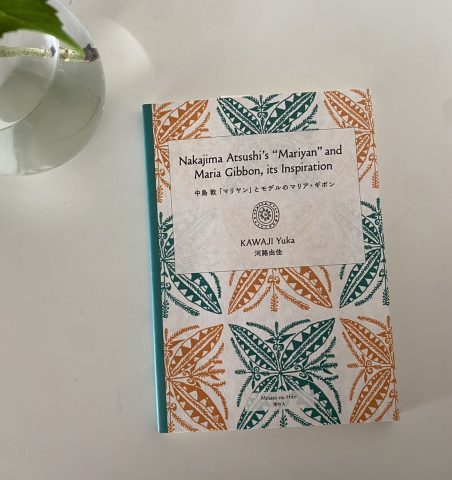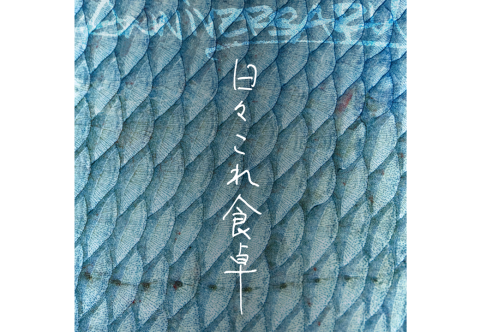昨年11月に開催された聖心女子大学にて行われた「TEDx USH」の登壇させていただいた様子が、TEDx talksのYouTubeオフィシャルチャンネルにて配信スタートしました。
オファーを頂いてから2ヶ月ほど、TEDx USHのメンバーと共に5回の打ち合わせ、資料の修正のやり取り、2度のリハを経て本番を迎えました。思い出深いこの体験を、ここに綴っておきたいと思います。
聖心女子大学は広尾の閑静な住宅街と賑やかな商店街の間にある、とても素敵なキャンパス。朝から時折浄化の雨が降る、良い空気の日曜日。
TEDxは米国でスタートした歴史あるシステムで「価値あるアイデアを広める」という精神に基づいて、大学やそれぞれの地域で自主的なイベントを開催するというプログラム。 私は、TEDxイベント自体に今回初めて参加したけれど、スピーカーさんだけでなく、パフォーマーさんがいたり、ワークショップが開催されたりと、1日がかりの総合的なイベントです。これを学生の皆さんが運営しているのだから、すごくいい。音響や看板や受付や紹介ボードまでお金をかけずにどうやったら効率良く作り出すことができるかと随所に工夫が見られます。

ついつい、私たちの重ねてきた歳月長め目線では、役割や担当箇所とかに目がいってしまうけど、彼らは全部やる。一人が何役もこなしていて、マルチタスク。他大学からの助っ人TEDxボーイズもテキパキ動いていてワンチームになっている。皆さん携帯にインカムアプリをダウンロードして耳にイヤフォンを装着。何がしかのアプリで常に共有が行われている。舞台でのリハが終わる瞬間に、全員が打ち込んだコメントがすぐに共有される。フィードバックの速さに度肝を抜かれる。そして、その指摘がもちろん忖度もしていなければ、お見事な視点で、うう、確かに!という粒揃いのダメだしを受け取る。(私の場合、笑顔が足りないとか、ジェスチャーが少ないとか色々)
これがアルファ世代なのか!?基本前向きな波動しか漂っていない。そんな風に過ごした午前中、いつの間にか登壇予定のスピーカー4名で意気投合し、本番に向けて一緒にお弁当を食べたりしながら、お互いの緊張をほぐしたり励まし合ったりしながら、その時を待つ。

1人に与えられたスピーチ時間は18分。この時間を超えてしまうと、TEDxのオフィシャルアーカイブに残らないらしい。過酷!せっかくここまで練り上げてきたんだから、ドキドキはするけど残りたい…。みんなでそう言い合って拳を握り合う。
果たして。
スポットライトが当たる壇上で人は、(どんなに仲間が応援してくれていても)一人なのだと私は思っていました。しかし、スタートして100名のお客様の前に立った時、なんとなく心地よい安心感がある。その正体は、スクリプトをめくってくれているスタッフ、スライドを進行してくれているスタッフ、タイムを見守ってくれているスタッフ、チームの存在でした。予定よりアドリブ多めの進行になってしまいましたが、なんとか喋り切って終了をタイムを見ると17:46!ギリギリの着地、いつだって、私の人生はギリギリだもの、予想の範囲内!
今回は「感覚の解像度をあげよう」と言うテーマで話をしました。自分の感覚を大切にして欲しいと言うメッセージを込めて作った構成です。蓋を開けてみたら、私以上にこの原稿とスライドに思いを寄せてくれたチームスタッフたち。この写真の方が絶対にいい。最後の終わり方はこうして欲しい。削られないように交渉してきます!などなど。

会場の定員は100人と決まっているようでした。

終了してホッとしているところ。

ともにこの日を乗り越えたスピーカーの皆さん。左から赤星麻里さん、宮野浩史さん、増田美玖さん。

Tedx USHの運営チームの学生さんたち。ずっと伴走してくれました。
誰よりも自分自身の感覚の解像度を高めて、感性を全開にしてやり遂げてくれたスタッフたちは、本当に輝いていました。わずか2ヶ月弱一緒に過ごしただけだけど、放つ言葉が変わっていく彼女たち。本番当日はもはや、頼もしくて眩しかった。学生たちのピュアなエネルギーに触れているだけで、私も沢山の気づきをもらいました。そして何かを伝えようともがく人は、すごく良い、と言うことに触れることができた。
実は今回、このオファーをくれたのは、大学時代からの親友の娘さんでした。この長い時間の友情の先にこんなサプライズがあったなんて!と巡り合わせの感謝です。素敵な大学生に育った彼女の中に時折お母さんのエッセンスを感じながら、また、しっかりと娘の生き方を見守る母の姿に感無量でした。
間違いなくこの先振り返った時に、あの地点で私の人生は変化したんだと思える時間でした。この機会をくれたTEDx USH、本当にありがとう。